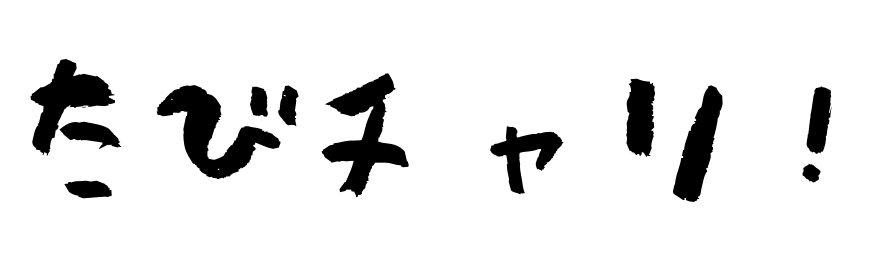自転車のパンク修理を自分でやってみたのだけど、失敗しちゃって。
- 何が原因なのだろう?
- やり直しはできるのかなあ?
こんなお悩みを解決します。
【この記事で分かること】
- 自転車のパンク修理に失敗した原因
- パンク修理(パッチ貼り)のコツ
- やり直しはできるのか?

自転車ショップで働く中で、無数にパンク修理をこなしてきた私が解説します。
お客様の「失敗した例」を数多く見てきた経験から、「何がダメなのか?」をアドバイスしますね。参考にどうぞ。
自転車のパンク修理に失敗!よくある原因5選+コツ

結論から言うと、よくある原因は下記の通りです。

パンク修理をご自身で行われる方は多いのですが、しっかり出来ている方って非常に稀です。
「自分で修理したんだけど空気が抜ける」というパターンは何度も見てきました(笑)
パンク修理って実は難しくって、少なくとも10回以上はやらないとマスターできないと思います。
今回はよくある失敗例をお話ししますので、自分に何が足りないのか参考にしてください。
そもそもパンクの原因が除去できていない


そもそも「パンクの原因が取り除けていない」というパターンは多いです。
真っ先にやらなければいけないことです。
「パンク修理(チューブ交換)」をする上で一番大事なことって何だと思いますか?
修理技術ではなくて、「原因を突き止め、取り除くこと」だと思っています。
パンクと言っても原因は様々です。
修理をするのはこの“原因”を突き止めてからです。
私たち整備士は原因が分かるまではチューブを元に戻しません。
もちろん中にはどうしても分からないものもありますが、基本的に原因を見つけるまでくまなく探すんです。

理由は「原因が分からないまま修理をしても、また同じ原因でパンクをしてしまうから」です。
靴に長い釘が刺さって足の裏を怪我したとして、絆創膏だけ貼ってオワリみたいなもの。
「いやいや、靴に刺さってる釘抜かなきゃまた怪我するやん!?!?」って話です。
異物が刺さっているならそれを抜かなきゃいけないし、タイヤに穴が開いているならタイヤ自体を交換しなければいけない。
摩耗なら空気圧不足が原因だから異物は無いと推測できるし、リム打ちも空気圧不足だからタイヤ側には問題がない可能性が高いわけです。

でも、必ず問題がないことを一度確認するのです。
その上で修理をします。チューブを元に戻します。
「パッチを貼る」ことだけがパンク修理ではないんですね。
なので、まずはパンクの原因を必ず突き止めてください。修理するのはそれからです。
やすりがけが不十分

ゴムのりを塗る前にやすりがけをしますが、これが不十分な場合が多いです。
しっかりゴミを除去し、接合面積を増やしてください。
やすりがけが不十分だと以降の作業が完璧でもくっつきません。
だいたい、パッチを貼る1.5倍-2倍くらの面積をやすりがけしましょう。
チューブの表面がテカテカツルツルの状態から、一皮むけてくるまでですね。
ここを丁寧に、時間をかけて行ってください。
ゴムのりが上手く塗れていない/塗りすぎ/乾燥していない

ゴムのりを塗る作業も結構難しいですね。
- パッチを貼る面積だけ濡れていなかったり。
- 塗りすぎだったり。
- 乾燥前にパッチを貼ってしまったり。
パッチを貼る1.5倍くらいの面積を、軽く塗り、必ず乾かしましょう。
3分くらい待てばOKですね。表面の水っぽさが無くなっていればいいです。
でも確認のために手では触らないように。くっつきにくくなります。

手順としては、あとは圧着です。
ゴムのりは接着剤とは違います。化学反応によってゴムを溶かしつつチューブとパッチを一体化させてくっつけています。
パッチをチューブに貼ったら、タイヤレバーで押したり、ゴムハンマーでトントンたたいたりしましょう。

最後にパッチのビニールを剝がした時、パッチのフチが全て「ピタッ」とくっついていれば成功です。
一か所でも「ビラッ」と浮いていたりしたらアウトです。爪を引っかけてピラピラなったらダメ。
後に必ず剥がれてくるのでやり直してください。
100均のパッチを使っている

割と整備士の中で話したりするのですが、「100均のパンク修理パッチ」はくっつきにくいです。
周りがオレンジ色のやつですね。(笑)
あのパッチを使っている時点で失敗する可能性が高い…というかいわば“ハンデ”を背負ってる状態です。
パッチは「マルニ」のモノを使うのがいいです。自転車屋が使っているのもコレです。
対象のチューブが細い(目安:28C未満)

チューブが細くなるほどパッチは貼りにくくなり、失敗する可能性が高くなります。
最初は28C以上(ママチャリなら1-3/8以上)のチューブにした方が無難ですね。
ロードバイクで使われるような23C、25Cタイヤは自分でも難しいです。
もちろん貼れないことはないのですが、パッチがチューブからはみ出すので、ずらしながら貼らないと行けなかったりするんですね。
その工程で上手くいかないことがあるので、まあ難しいですよ。
仮に貼れたとしても圧着が弱いと空気圧で剥がれてきたりするので、基本細いチューブなら「チューブ交換」をした方がいいです。
お店で修理をするにしてもそういわれると思います。
パンク修理のやり直しは可能?

パンク修理のやり直しは可能です…が、しっかり掃除しないと2回目以降の貼り付けが難しくなります。
まずは汚くなった表面のゴムのりを落としましょう。
パーツクリーナーをかけるとヌルッとするので、タオルでふき取りましょう。
タオルで拭くと細かい糸が付着しますから、再度軽くやすり掛けを行います。
チューブの表面にゴミがなく、きれいになったら、もう一度ゴムのりからやり直します。

何度もやり直すとチューブが薄くなりすぎて破裂します。
まあ、2回目で失敗したらチューブ交換した方がいいかなと思います。
お店に任せた方が安上がりの場合もよくある

安上がりになるからと自分でパンク修理される方も多いのですが、それを失敗して店に持ち込むとなると、場合によってはチューブ交換しかできない場合もあります。
余計高くつく羽目になるので、注意してください。
初心者がパッチ修理にしっぱいした状況のチューブは、状態が悪いことが多いです。
「やり直そうにももう無理だよな…」みたいな感じで、チューブ交換を余儀なくされます。
パンク修理だったら1000円程度で済んでいたものが、チューブ交換となると費用がかさみますよね。
なので、下手に自分ではやらず、実は最初から店に持ち込んでいた方が安くなるケースって多々あるんです。

「勉強をするため」にパンク修理するのはいいと思いますが、上手く貼れる人は少ないです。
自身がないなら「お店に任せる」という選択肢が賢いと思います。
<注意>パッチの代用は基本無理
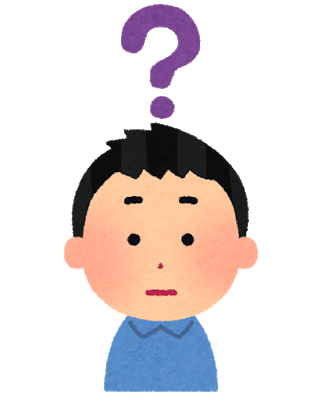
パンク修理のパッチって、ガムテープやチューブの破片で代用できないのかな?
パッチを買わなきゃダメ?
…中にはそう考えている人もいるかもしれません。実際によくいます。
結論「無理」です。
ガムテープで絶対に穴はふさがりません。
チューブを薄く切って…というのはできないわけではないですが、難易度が高すぎて初心者にはまずできないと思います。せめてパッチが上手く貼れる人じゃないとできないでしょうね。
自分もチャレンジしてみたことありますが、全くだめでした。
素直にパッチを買ってください。
まとめ
最後に、本記事の要点をまとめます。
【自転車のパンク修理に失敗!よくある原因5選+コツ】
- そもそもパンクの原因が除去できていない
- やすりがけが不十分
- ゴムのりが上手く塗れていない/塗りすぎ/乾燥していない
- 100均のパッチを使っている
- 対象のチューブが細い(目安:28C未満)
上記を参考に、パンク修理に再挑戦してみてください。
最初は太めのチューブでやってみることをオススメします。
あ、再三ですがパンク修理は「異物を除去すること」「パンクの原因を突き止めること」が何よりも大切です。お忘れなく。